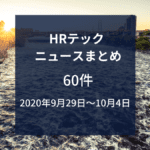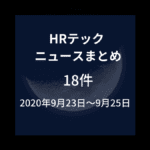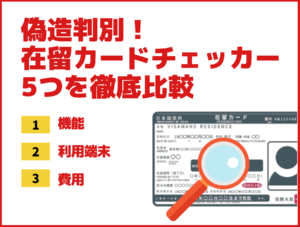HRTech業界でよく使われる用語まとめ

「Human Resources」と「Technology」を組み合わせた造語であるHR Tech。
今回紹介する用語の種類は人事に関する言葉(アメリカなどで使われている言葉がそのまま使われることが多い)、テクノロジーに関する言葉の大きく2つに分けられます。
本記事では、この春からHR Tech業界に入ってこられた方やHR Tech関係の事業を始められた方のためにHR Tech業界でよく使われる用語を解説いたします。
- AI(artificial intelligence)
- Alumni(アルムナイ)
- AR(Augmented Reality)
- ATS(Applicant Tracking System)
- Bigdate(ビッグデータ)
- Block Chain(ブロックチェーン)
- Chatbot(チャットボット)
- Check-ins/1on1s
- CHRO(Chief Human Resource Officer)
- Cloud(クラウド)
- Crowd Sourcing(クラウドソーシング)
- Direct Recruiting(ダイレクトリクルーティング)
- Employee Experience(エンプロイー・エクスペリエンス)
- Engagement(エンゲージメント)
- Entry Management(エントリーマネジメント)
- Exit Management(イグジットマネジメント)
- HCM(Human Capital Management)
- Holacracy(ホラクラシー)
- HR(Human Resources)
- HR Tech(Human Resources Technology)
- HRIS(Human Resource Information System)
- IoT(Internet of Things)
- MR(Mixed Reality)
- Off-Boarding(オフボーディング)
- OKR (Objectives and Key Results)
- On-Boarding(オンボーディング)
- Organizational Network Analysis (ONA)
- Peer Feedback
- People Analytics(ピープルアナリティクス)
- Performance Management(パフォーマンスマネジメント)
- Recognition(レコグニション)
- Referral Recruiting(リファラル採用)
- Retention(リテンション)
- RPA(Robotic Process Automation)
- SaaS(サース)
- Social Recruiting(ソーシャルリクルーティング)
- Talent Management(タレントマネジメント)
- Talent Pool(タレントプール)
- VR(Virtual Reality)
- Well Being(ウェルビーイング)
- Wellness(ウェルネス)
1.AI(artificial intelligence)
人工知能を意味する。解釈は研究者によっても異なるが、「人工的に人間の知能を模倣するための概念および技術」のことを指す。
2.Alumni(アルムナイ)
元は大学の卒業生を指す言葉。最近では、企業のOB/OG(転職・離職者)を指す言葉としても定着してきた。
参考:アルムナイとは〜注目されている背景と活用のメリット〜
3.AR(Augmented Reality)
拡張現実(Augmented Reality)の略。現実空間に付加情報を表示させ、現実世界を拡張する技術。
4.ATS(Applicant Tracking System)
採用管理システム。応募者の募集から採用決定までの一連の人事業務を管理するシステム。
5.Bigdate(ビッグデータ)
一般的なデータ管理・処理ソフトウエアで扱うことが困難なほど巨大で複雑なデータの集合。HR分野では、社員の就業時やスキルなど、とても多くの情報が存在する。
6.Block Chain(ブロックチェーン)
Block Chainの略。日本語では台帳と言われます。ビットコインを例に挙げると、ブロックとは、「一定期間内の取引の塊」のことで、チェーンとは、その一つ一つが繋がっている状態を指す。
7.Chatbot(チャットボット)
チャット(Chat)とロボット(robot)を組み合わせた言葉。テキストや音声を通じて、会話を自動的に行うプログラムで、人工無脳などと呼ばれる。
8.Check-ins/1on1s
9.CHRO(Chief Human Resource Officer)
Chief Human Resource Officerの略。CHOと言われる場合もある。
最高人事責任者を指す言葉で、似た言葉には、最高経営責任者:CEO(Chief Executive Officer)や最高執行責任者:COO(Chief Operating Officer)、最高技術責任者:CTO(Chief Technical Officer )などがある。
10.Cloud(クラウド)
インターネットを通じて、サービスを必要な時に必要な分だけ利用する考え方。クラウド型の勤怠管理システムなどが多く存在する。Google DriveやiCloud、Dropboxなどが有名。
11.Crowd Sourcing(クラウドソーシング)
Crowd(群衆)とSourcing(業務委託)を組み合わせた言葉。
インターネット上で不特定多数の人に対して、仕事を発注する方法。アウトソーシングとは違い、必ずしもプロが担当してくれる訳ではない。
12.Direct Recruiting(ダイレクトリクルーティング)
求人広告や人材紹介会社を通す「待ちの採用」ではなく、自社のデータベースやSNS、イベント開催などを通して行う「攻めの採用」。
13.Employee Experience(エンプロイー・エクスペリエンス)
従業員が組織や会社の中で体験する経験価値のこと。会社への入社前から採用プロセス、入社後の研修や配属、評価や異動、退職までの、全てのプロセスにおいて発生している。
14.Engagement(エンゲージメント)
所属する組織への愛着心・帰属意識。組織へのエンゲージメントを高めることで、業績アップ、離職率の低下、組織力の向上などが期待される。
15.Entry Management(エントリーマネジメント)
雇用の入り口にあたる採用などを戦略的に計画・管理する人材マネジメント。
16.Exit Management(イグジットマネジメント)
雇用の出口にあたる退職などを戦略的に計画・管理する人材マネジメント。
17.HCM(Human Capital Management)
Human Capital Managementの略。社内教育や研修参加、職業訓練などの教育を施すことで人材という資本を拡大し、その資本を実験的プロジェクトの実施やイノベーションの創出などの組織内活動に対して積極的に投資することでリターン(業績)の最大化を目指す。
18.Holacracy(ホラクラシー)
階級や上司・部下の関係が一切存在しない組織の管理体制で、中央集権型、ヒエラルキー型とは真逆の考え方。
19.HR(Human Resources)
Human Resourcesの略。人材育成や採用活動、人事評価などの人事領域の業務。
20.HR Tech(Human Resources Technology)
従来の人事業務に、AIやクラウド、ビッグデータなどといったテクノロジーを掛け合わせた造語。Human Resource×Technology。
参考:HR Techとは〜注目されている背景と市場の盛り上がり〜
21.HRIS(Human Resource Information System)
Human Resource Information Systemの略。給与・勤怠・採用・労務などの人事業務とITを組み合わせ、自動化・効率化するシステム。
22.IoT(Internet of Things)
Internet of Things(モノのインターネット)の略です。センサーと通信が可能なモノ(PC/スマホ/機械/ウェアラブルデバイスなど)を、インターネットへ接続することを指す。
23.MR(Mixed Reality)
複合現実(Mixed Reality)の略。CGなどで作られた人工的な仮想世界に現実世界の情報を取り込み、現実世界と仮想世界を融合させた世界をつくる技術。
24.Off-Boarding(オフボーディング)
25.OKR (Objectives and Key Result)
目標(Objectives : 何を実現したいか)と目標達成度の指標となる主な結果(Key Results : 実現のために必要な成果)をリンクさせ、会社やチーム、個人が向かうべき方向とやるべきことを明確にする目標管理手法。
26.On-Boarding(オンボーディング)
新規採用した人材の受け入れから定着、戦力化までの一連の流れ。組織の文化やルール、仕事の進め方などにいち早くなじませ、パフォーマンスを引き出すための教育・訓練プログラム。
27.Organizational Network Analysis (ONA)
コミュニケーション、情報、意思決定がどのように組織内を流れるかを視覚化する構造化された方法。
組織ネットワークは、組織内の情報がどのように流れているのかを理解するための基盤となるノードと結びつきから成り立っている。
28.Peer Feedback
上司・部下間だけでなく、同僚同士でフィードバックを交換すること。
29.People Analytics(ピープルアナリティクス)
人事に関連する情報や数字を収集・分析して、客観的なデータを使って、採用、教育、評価といった一連の人事業務の意思決定に役立てること。
参考:ピープルアナリティクスとは~Googleも勧めるHRの重要テーマ〜
30.Performance Management(パフォーマンスマネジメント)
従業員の能力とモチベーションを引き出しながら目標を達成するマネジメント手法。
31.Recognition(レコグニション)
社員同士のコミュニケーションのうち、特に賞賛に関することを活発化させる仕組みのこと。
32.Referral Recruiting(リファラル採用)
在籍する社員やアルバイト、OB・OGなどの紹介により、自社の社風に合っている人や、業務内容に適した人を選考、採用する方法。
33.Retention(リテンション)
34.RPA(Robotic Process Automation)
Robotic Process Automationの略。ロボットによる業務自動化の取り組みを表す言葉。
ロボットとは、「人間が行う作業を代行できる」「人間と比較したときに圧倒的な能力を持っている」「ルール変更など環境の変化に強く、柔軟性がある」という3つの特徴によって定義されるもので、実体がなくソフトウェアの場合でもロボットと定義される。
35.SaaS(サース)
Software as a Serviceの略。サービスとしてのソフトウェアという意味で、アプリケーションをインストールするのではなく、クラウド経由で提供されるサービスを指す。
36.Social Recruiting(ソーシャルリクルーティング)
ブログやTwitter、Facebook、YouTubeなどソーシャルネットワークサービス(SNS)を活用した採用手法の一つ。
37.Talent Management(タレントマネジメント)
社内の優秀な人材(タレント)のスキルなどを把握し、そのタレントのパフォーマンスを最大限に活かすための戦略的な人材配置や教育などの取り組み。
38.Talent Pool(タレントプール)
採用候補者になりうるデータベース。採用プロセスの中で、不採用になったり、内定を辞退した人たち、退職/転職者も含まれる。適切なタイミングが訪れた時に、採用できるよう、継続的なコミュニケーションなどが求められる。
39.VR(virtual reality)
仮想現実(virtual reality)の略。仮想空間上に人工の環境を作り出し、そこにいるかのような感覚を体験できる技術。
40.Well Being(ウェルビーイング)
「①心身ともに健康である状態(ウェルネス)」に加え、「②モチベーションや目標の有無」「③良好な人間関係」「④金銭的安定性」「⑤コミュニティへの帰属意識」なども重視する全体論的アプローチである。
41.Wellness(ウェルネス)
心と体の健康のこと。企業が従業員の心身の健康を経営資源と捉え、健康促進を戦略的に実践することを「ウェルネス経営」や「健康経営」と呼ぶことが多い。